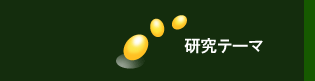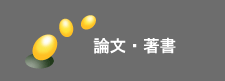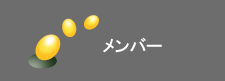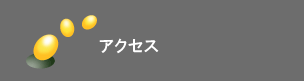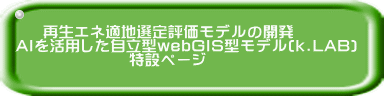名古屋大学未来材料・システム研究所
名古屋大学大学院工学研究科土木工学専攻
環境共生・生態システム(エネルギー・環境エコロジーシステム)協力講座
林 研究室
Hayashi Lab., Nagoya University, Institute of Materials and Systems for Sustainability
Nagoya University, Graduate School/ School of Engineering, Civil and Environmental Engineering,
Environmental Symbiosis and Ecology System (Energy and Environmental Ecology
System) Cooperation Laboratory
|
 |
 |
|
|
ゥ然共生型ミ会実現のための再生可能エネルギーと環境エコロジー・システム評価に関する研究
本研究コでは、以下の研究分野の研究を進めています。
エネルギー・環境の影響評価を行い、搗ア可能な社会実現のための研究を行っています。特に、土地利用や自然環境の空間評価に着目し、再生可能エネルギー(バイオマス、小水力、太陽光等)、生態系サービス、経済社会に関する課題の総合的な解決に取り組んでいます。現地調査レベルの小さいスケールから国を超えたグローバルなスケールまでの影響評価を行うとともに、GIS(地理情報システム)等の空間分析、AI、ドローン、現地調査等を組み合わせた学際的なアプローチで研究に取り組んでいます。
|
|
蛯ネキーワードは以下のとおりです。
- エネルギー・環境システムの空間評価
- バイオマス、小水力、太陽光等の再生可能エネルギーの空間評価
- ゥ然環境、生態系サービス等の空間評価
- AIやドローン、GIS(地理情報システム)を用いた空間分析
- 現地調査からグローバル評価までの多様な環境評価と統合評価
- 各墲フ環境影響評価や環境政策、再生可能エネルギーのシステム分析
- 国際環境協力にかかわる研究
- など
|
|
|
|
| |
| ▼▼▼研究コの主な活動 |
|
|
 |
| |
| ▼▼▼現在進行中の研究 |
| |
| GIS等を用いた土地利用に関わる環境評価に関する研究 ー バイオマス・エネルギー環境評価 |
| |
共同研究:国立環境研究所福島x部
-----------------------Under consutraction
衛星やGISデータを用いたエネルギー・環境評価
都sや県スケールのエネルギー・環境・生態系サービスの空間評価については、衛星データやGISデータ等を用いて空間分析を行っている。
名古屋市、豊田sなどを中心とした愛知県、東海地域などの国内の空間分析とともに、ミャンマー、ラオスなど途上国で適用可能な評価手法の開発を進めている。
開発したエネルギー・環境影響評価手法を、下段に記述するAIを用いたグローバルモデルであるk.LABに取り込むことにより、グローバル・エネルギー・環境評価の日本モデルの開発を進めている。
|
| UAV(ドローン)を用いた省エネ型バイオマス・炭素固定量推計阮@の開発 |
共同研究:中部大学国際GISセンター、大阪大学
-----------------------Under consutraction
UAV(ドローン)を用いて針葉竝L葉ネどの森林のバイオマスおよび炭素固定量の推計阮@の研究を進めている。ドローンの季節画像の活用、動画の活用などを通じて、酔疚な3沍ウ画像の作成や炭素固定量推計阮@の開発を行っている。調査対象地域は、岐阜県高R、中津川、愛知県名古屋市、春日井市などでである。
また、森林の現地調査により、網羅的かつ総合的な森林生態系サービス情報の収集を進めてきた。これまでに、名古屋市内の森林、高Rの強度間伐ヒノキ林、皆伐のカラマツ林、中津川の間伐スギ林、春日井市の社寺林などの調査を行い、データの収集を行っている。
|
|
愛知県西部地域の各墲フ生態系サービスの空間評価
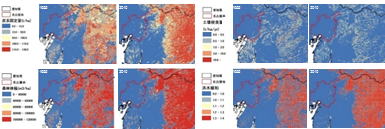
UAV(ドローン)を用いた森林のバイオマス量および炭素固定量の
推計に関する研究
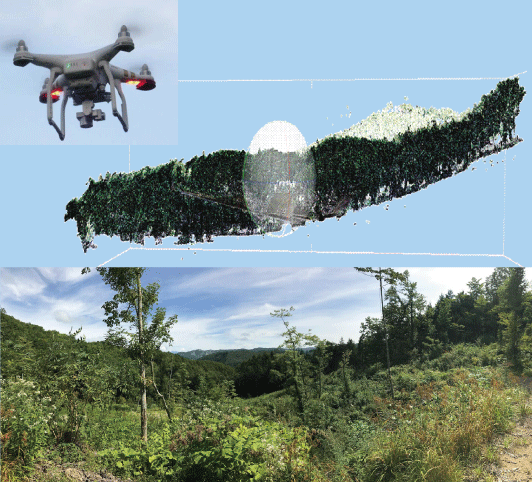

|
| |
| LCAを発展させた持続可能性評価ツール開発 |
| |
共同研究:国立環境研究所
-----------------------Under consutraction
搗ア可能な社会を実現するという目標を評価するツールとして、Life Cycle Assessment (LCA) を拡張した、新しい総合的な評価手法の研究を実施している。特に、環境容量を踏まえつつ、條ヤの概念を取り入れた資源占有の時間フットプリントRTF)評価手法の開発を進めている。
|
糟ケ占有の時間フットプリント:Resources Time Footprint(RTF) (Fujii, Hayashi, Ooba, 2014)
特徴
RTFは、以下のような特徴を有する持続可能性を評価する手法である。
- 省エネ型で希少資源消費量も少ない製品等の評価
- 環境(CO2排出量等)、糟ケ(鉱物資源等)、労働量、土地(人為的土地利用)のトレードオフ
- 糟ケや汚染物質の環境負荷等の占有期間等の時間評価
- 土地制約を考慮する持続可能性総合評価手法
RTFの詳細については、後日HPを解説する予定。
Resources Time Footprint(RTF) (Fujii, Hayashi, Ooba, 2014)
Identification of potential locations for small hydropower plant based
on resources time footprint: A case study in Dan River Basin, China(x.Huang,
K.Hayashi, M.Fujii, F.Villa, Y.Yamazaki, H.Okazawa,2023)
Resources time footprint analysis of onshore wind turbines combined with
GIS-based site selection: A case study in Fujian Province, China(X.Huang,
K.Hayashi, M.Fujii, 2023)
|
|
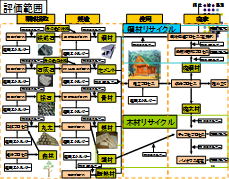 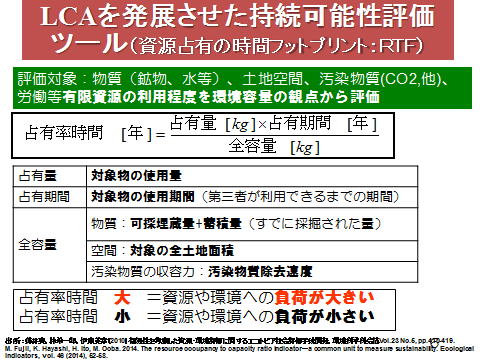 |
| |
AI(人工知能:セマンテック,オントロジー)を用いた統合型エネルギー・環境影響評価モデル
|
| |
共同研究:bc3(バスク気候変動センター,スペイン)
k.LAB Japan(名古屋大学、国立環境研究所、
大阪大学、中部大学、東京農業大学他)

-----------------------------------------ARIES project
スペインbc3のFerdinando Villa教授らが開発した、AI(人工知能)のオントロジーとセマンティクスを活用した統合評価プラットフォーム(k.LAB)を用いて、日本モデル構築に向けての基礎的研究を進めている。
K.Lab Japan:
■■■
k.LABの日本モデルの開発を行うための勉強会を2017年7撃ノ設立し、数ヶ撃ノ一度のペースで会合を開催している。メンバーは、名古屋大学未来材料・システム研究所林研究コ、大阪大学工学研究科町村研究コ、中部大学国際GISセンター杉田准教授、東京農業大学生産工学科怨゙V研究コ、鳥取大学R崎准教授等である。
活動の詳細について,特設ページを解説しました。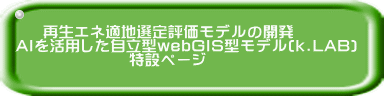
|
特徴
- セマンテックス、オントロジー等によるAI(人工知能)
- 多様な環境項目の重層的評価
- ローカルからグローバルのシームレスな空間評価
- Ecosystem serviceからエネルギーへの拡張
- エネルギー・環境評価への拡張
|
|
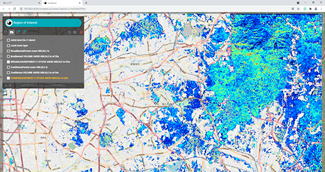
グローバル評価の日本モデルの開発
|
| |
|
| |
|
| ▼▼▼これまでの主な研究プロジェクト |
|
| |
最先端・汾「代研究x援開発プログラム
生物多様性政策で活用可能な生物多様性・生態系サービスの総合評価手法の研究(H22-25年度末)
|
| |
■■■詳細はこちら |
|
|
 Top pageに戻る Top pageに戻る
Copyright (C) 2018 Hayashi Lab. All Rights Reserved. 2018/10/08updated
|


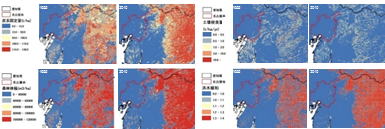
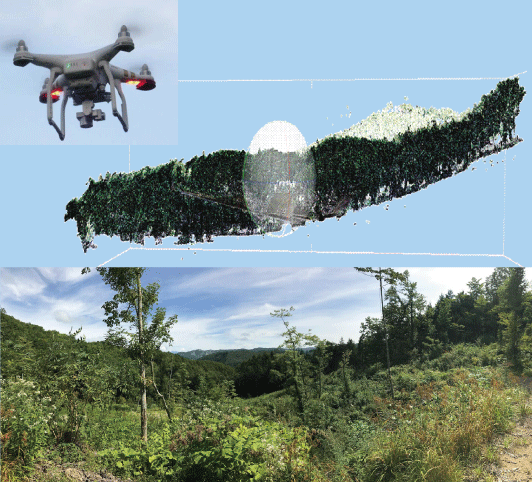

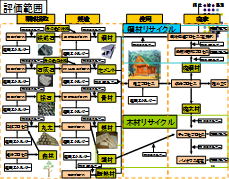
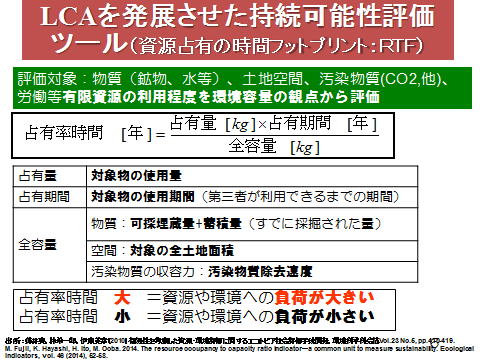
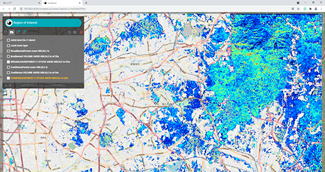
 Top pageに戻る
Top pageに戻る